福島には漁業がある(前編)

「福島の漁業」と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべるだろうか。
正直なところ、多くの人がその実態を想像するのが難しいのではないだろうかと思う。
漁業者をはじめ、地元で頑張って挑戦する人々の姿が積極的に伝えられる一方で、処理水放出や賠償についてなど、触れるのをためらってしまうような“タブー感”のある話題があるのも事実。そのことに目を背けてしまったり、繊細に扱ってしまう気持ちもよく分かる。
しかし実のところ、そういった「語りにくさ」の中に、福島の漁業が抱える課題の本質が隠されているようにも感じる。
いわき市の漁師の家に生まれ、ずっと水産業界で働いてきた私でさえ、地元で沿岸漁業を営む父に何でも聴けるわけではない。大好きな人たちを傷つけてしまうのではないかという恐れから、「福島の漁業の今」について、ずっと踏み込めずにいたのだ――。
今回は、いわきの漁師を父に持ち、自身も10年以上水産業界で働いてきた筆者が、改めて地元の漁業の“今”を伝える。専門家のような語り口というよりも、あくまで「漁師のむすめ」の視点から、私が気が付いた大切な事実を読者の皆さんと共有していきたい。漁師と故郷が大好きな筆者の主観が大いに入ったコラムだが、ぜひ気軽に読んでいただけたらと思う。
“漁業関係者”から“漁業当事者”になる

タコかご漁を手伝うむすめ(妹)。揺れる船上で、まだ足元がおぼつかない。
2011年の東日本大震災当時、私は東京で大学生をしていた。震災が起こってから、地元の漁業のためにできることを考えてはみたものの、原発事故による出口の見えない状況を目の前に、福島の漁業が抱える課題は自分にとって大きすぎるものとなっていた。
それでも、「いつか地元の漁業のためになにかしたい」と淡い希望を抱き、東京で水産団体の職員として就職をした。直接地元に関わることはできなくとも、”漁業関係者”としての道を選んだのだ。
一生懸命打ち込むうちに、次第に仕事に追われるようになり、結婚をして生活が安定していった。日々の暮らしに慣れるのとは反比例して、「いつかいわきの漁業のために」というその”いつか”は、どんどん遠い未来として薄れていった。
そんな中、私の背中を押す大きな出来事があった。
2023年8月、福島第一原発からの最初の“処理水”が放出されたことだ。
ここで賛否を争いたいわけではない。
今では福島の魚が全国の店頭に並び、消費者の元に届いている。この状況に辿り着くまでにどれだけ多くの人々が力を尽くしてきたことか。そのことを少しでも知っている自分だからこそ、この十数年の努力が振り出しに戻ったらどうしようという不安があった。人々の価値観の対立が再び起こってしまうことへの嫌悪感や、何とも言い切れない悔しさが募った。
科学的な説明は理解しつつも、得も知れぬ不安と焦燥感にさいなまれたのだ。
一方で、「ちゃんと当事者にならないと」という気持ちも湧き上がってきた。
今の私に何ができるのか、福島の漁業の現場にどんな課題があるのか、“漁業関係者”という道を選びながらも、実は何も分かっていなかったことに気が付いた。
地元に滞在して、浜に行き、漁協に行き、話を聴きたい ――。
翌月の9月、理解のある夫からのエールをもらい、私は現在の自宅がある首都圏といわき市とでの二拠点生活を始めた。
漁師の娘が見た「いわきの漁業の今」
いわきでの最初の一ヶ月は、とにかく家業の現状を観察することから始めた。
ここからは、私が見た実態の一部をご紹介したい。
(注)あくまでいわき市の沿岸漁業者の一例で、漁家によって様々な実態があります。

夫婦で漁にでる両親。言葉少なだが阿吽の呼吸でタコかごを揚げる。
震災の前までいわき市では、「チャッカ船」と呼ばれる小型船に夫婦で乗り、漁に出る漁家がちらほら見られた。私の実家でも父と母、その先代は祖父と祖母が、一緒に船に乗りシラスやタコなどを獲っていた。漁は、季節や海の状況によって網や漁具を変えながら柔軟におこなわれる。
船に乗らない家族も、水揚げや陸(おか)仕事を手伝い、子どもたちは浜に連れて行かれて親が働く傍らで遊んでいたりする。それが港の光景だった。
東日本大震災後から13年経とうとしている今でも、休漁や試験操業などを経て、操業規模がなかなか元には戻らない状況が続いている。父は独りでもできる漁法を選んで操業をすることが多くなり、母はたまに漁を手伝いながらパートの仕事をメインにするようになった。
他の家族が港で手伝いをすることはなくなった。
震災当時、40代だった父は還暦を迎えている。様々なできごとに左右されながら、長い時間をかけて体力に合わせた今のやり方に落ち着いたのだ。
二拠点生活を始めてから、市場での水揚げ作業も手伝うようになった。
震災前と操業の形が変わったこともあり、市場には私にとって新鮮な風景が広がっている。以前は一日に数十キロ、数百キロを水揚げしていた漁師たちが、一匹ずつ丁寧に活魚を扱う。私の原風景にある市場の圧倒的な量とスピード感とは違い、時間が丁寧に流れている感じだ。ここで詳しくは触れないが、この変化には賠償の仕組みも関係していると言う。
新しいいわき市の漁業風景を見ながら私が感じたのは、現状に対する「安堵」と、未来に対する「不安」だった。
「安堵」とは、あのような天災と人災があったにも関わらず市場に魚が揚がり、人が集って生業が続いている”奇跡”に対するもの。そして「不安」とは、この“奇跡”がこの先も続くのだろうかというものだ。
そしてその「不安」を煽るような課題も見えてきたのだが、それについては後編で触れていこうと思う。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
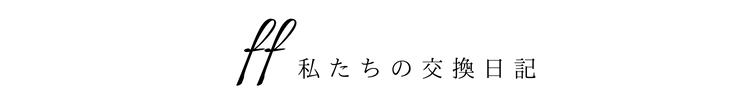
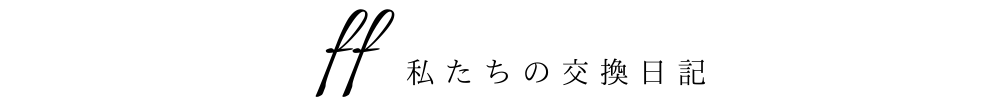




この記事へのコメントはありません。