”アップサイクル”って何だろう?意外と知らない”リサイクル”との違い。

「アップサイクル」という言葉、最近よく耳にしませんか?
SDGsが掲げる“持続的な開発目標”の中でもよく登場するこの言葉、一体どういう意味なのでしょうか。リサイクルとの違いは…?今回は、知っていそうで意外と知らない「アップサイクル」についての調査です。
アップサイクルとは何か?
アップサイクルとは、簡単に言うと「捨てられるはずだったものに手を加え、より価値のあるものにつくり代える」ことを指します。例えば、アパレルメーカーがデッドストックの生地を利用して新しい製品を生み出すなどがこれに当たりますが、大事なのは“元の状態よりも価値のあるもの”に変換されることです。
リサイクルとの違いは?
アップサイクルと似た言葉に「リサイクル」がありますが、この二つは区別して使われます。アップサイクルが廃棄されるはずの素材に付加価値を加え、新たな“製品”としてアップデートするのに対し、リサイクルは廃棄されるものを分解・資源化し、再利用するための“原料”へと変換させることを指します。
アップサイクルの良い点は?
では、アップサイクル独自の利点とは何でしょうか?アップサイクルと並んでよく使われる「3R(Reduce, Reuse, Recycle)」と比較しながら、そのメリットを見ていきましょう。
Reduce(リデュース)とは
Reduce(リデュース)とは英語での“減らす”という意味の通り、そもそものゴミの量を減らしましょう、という目標です。出てしまった廃棄物を利用するというアップサイクルとは根違い、まず「必要ないものは買わない、必要な分だけを買う」という、3Rの中でも最もはじめに実践されるべき行動指針として挙げられているのが特徴です。
Reuse(リユース)とは
Reuse(リユース)とは“再利用する”という意味の英語です。3Rでのリユースは「同じものをそのまま使う」という意味で定義されています。例えばフリーマーケットで不要なものを売り買いしたり、壊れたものを修理に出して再び使ったすることがリユースに当たります。“新しい価値を与えて変化させる”というアップサイクルに比べ、“同じものを使い続ける”というリユースでは、モノとしての寿命は短くなる傾向にあります。
Recycle(リサイクル)とは
Recycle(リサイクル)とは、前述の通り廃棄されるものを“資源の状態”にまで戻して再利用することを指します。元の素材に手を加えて昇華させるアップサイクルに比べ、一旦資源レベルにまで戻すリサイクルの方がエネルギーコストがかかる傾向にあります。
つまり、そもそもゴミを出さない・減らし(リデュース)、その上で出てしまった廃棄物を「リサイクル」より少ないエネルギー量で、かつ「リユース」よりも長く使える付加価値のあるモノにつくり代えるのが、「アップサイクル」の利点ということになります。
ファッションを中心に広がるアップサイクル
SDGsの波を受け広まりつつあるアップサイクルですが、特に目覚ましいのがファッション業界においての変化です。
現代のファッション業界のあり方にはたくさんの課題があります。ファストファッションに代表されるような「大量生産・大量消費」の仕組みと、そのために低賃金・過酷な環境下で労働を強いられる労働者。作れば作るほど売値は安くなりますが、それと比例して生産者を取り囲む環境は厳しさを増します。そんな中2013年4月24日、バングラデシュにある縫製工場が崩壊し1,138人が犠牲となった「ラナプラザ崩壊事故」をきっかけに、これまでのアパレル産業は大きな転換を余儀なくされました。
まずは「必要な分だけを買う」そして「長く使う」、その上で今ある余過剰分やどうしても出てしまう廃棄物には、価値をつけて新しくよみがえらせる。「エシカルファッション」という言葉に代表されるように、ファッション業界ではアップサイクルへの挑戦がいち早く進められてきました。
国内のアップサイクル事例3つ
海外を中心に勢いを増しているアップサイクルの取り組みですが、日本でも魅力的な取り組みが生まれています。
ここではff編集部の独断により(!)、国内の一押しアップサイクルブランドを3つご紹介します。
MUSKAAN
希少なヴィンテージ着物をアップサイクリングし、新たな価値を生み出すことをコンセプトとしている「MUSKAAN(ムスカーン)」。伝統的なテキスタイルが持つ独特の美しさは保ちつつ、現代のライフスタイルに合わせたデザインに落とし込んだクリエイションを展開している。
PLASTICITY
「10年後になくなるべきブランド」と宣言し、プラスチック傘のアップサイクル製品を販売する「PLASTICITY(プラスティシティ)」。世界的に見てもプラスチックの消費量が多い日本の現状を改善すべく、使い捨てや置き忘れのビニール傘をバッグやファッションウエアとして新しい製品へとよみがえらせている。
ReBuilding Center JAPAN
“リビセン”の愛称で親しまれる「ReBuilding Center JAPAN(リビルディングセンター ジャパン)」。ここでは解体される空き家から古材や使えそうな家具を“レスキュー”し、手を加えて販売したり、リノベーションのための部材として活用している。
福島のアップサイクル事例3つ
実は福島県にも素敵なアップサイクルの事例があります。まだまだ知られていない福島のアップサイクル事情をご紹介しましょう。
yashu
中島村を拠点として木工作家として活動する「yashu(やしゅ)」は、木材加工の過程で出た端材を利用して、花器などの木工作品を製作しています。家具職人としての技術を活かした丁寧な仕事が魅力的な作家です。
明日 わたしは 柿の木にのぼる
デリケートゾーンブランドとして展開している「明日 わたしは 柿の木にのぼる」は、国見町の名産「あんぽ柿」をつくる過程で出た“柿の果皮”を利用して成分を抽出しています。
古物屋 時雨
須賀川市に店舗を構える「古物屋 時雨(こぶつや しぐれ)」は、店主のセンスで選りすぐられた古物が販売されています。一見素通りしてしまいそうな“がらす瓶”や“おはじき”も、使い方の工夫で暮らしの中のアクセントとなることを教えてくれる場です。
アップサイクルで、暮らしの中の想像力を育む。
これまで見てきたように、アップサイクルは単なる「使いまわし」や「長く使う」ことではありません。今あるものをいかに“より良く”、“より魅力的に”そして“より丈夫に”できるかということをテーマとしているからです。一見価値が無くなったように見えるものも、見方を変えれば新たな魅力があるかもしれない。そう思うと、アップサイクルによって日々の暮らしの想像力を育まれるかもしれませんね。
今回ご紹介したアップサイクル製品を含め、ぜひ今後のアップサイクルの動きにもご注目下さい。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
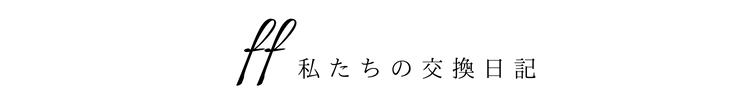
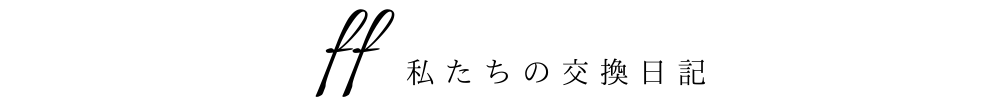



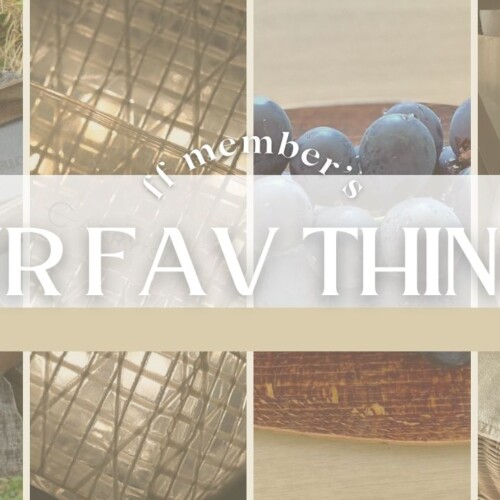
この記事へのコメントはありません。